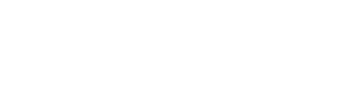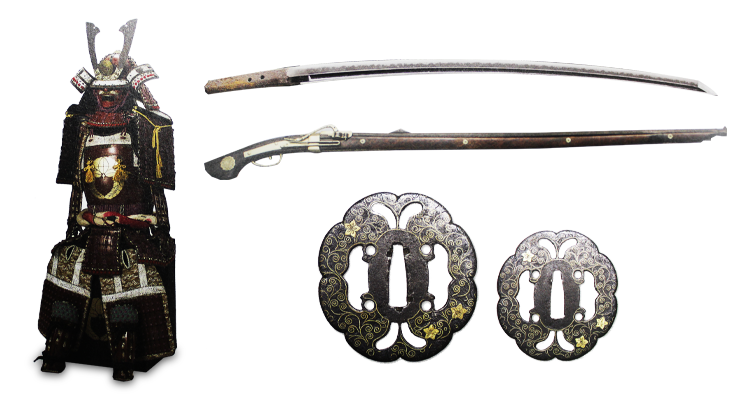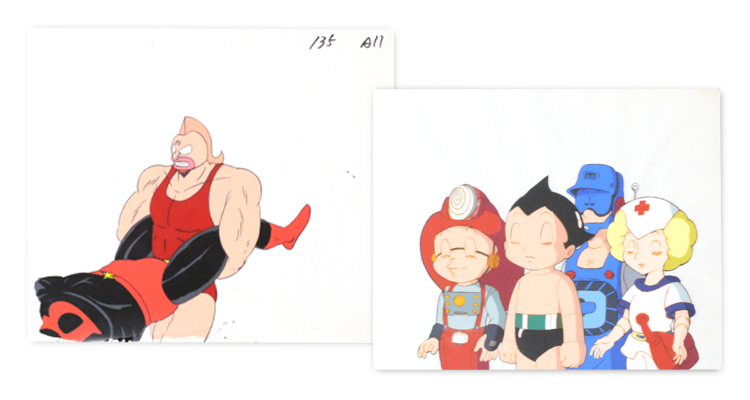1895年(明治28)、岡山県生まれの日本画家。幼い頃から絵を描くのが好きだった遙邨は、1910年(明治43)、15歳のとき大阪に出て松原三五郎の天彩画塾で洋画の手ほどきを受け、1914年(大正3)、19歳で第8回文展に水彩画「みなとの曇り日」を出品、初入選する。
その後、同郷の小野竹喬との出会いなどにより、次第に日本画に魅力を感じるようになり、1919年(大正8)には京都に出て、竹内栖鳳の門下生となる。この年の第1回帝展で「南郷の八月」が入選する。
大正時代後期の遙邨は、ムンクやゴヤに惹かれ、その影響のなかで、人間の哀しみや人生のはかなさに深く感応しつつ、新しい情趣に満ちた日本画の創造を試みた。1923年(大正12)に起きた関東大震災を描いた作品「災禍の跡」は、この時代の代表作である。
昭和に入り、遙邨の画風はさらに変化する。1928年(昭和3)、第9回帝展で「雪の大阪」が特選となり、1930年(昭和5)には第11回帝展で「烏城」が再び特選となる。これらの作品の中には、当時の風俗とそこに生きる人間をテーマにしたものも多く、大和絵の新解釈にたった清新な作風によって、遙邨は再び画壇に認めらた。また、この時期、江戸の浮世絵師・歌川広重に傾倒し、自らも3度にわたり東海道を徒歩で写生旅行している。その集大成となったのが、1931年(昭和6)に完成した「昭和東海道五十三次」である。
昭和10年代には日本画の巨匠・冨田渓仙の作風に共鳴した時期を経て、戦後には装飾性やユーモアに富んだ独自の表現に到達し、風景画に一境地をきり開いた。「幻想の明神礁」や「森の唄」はこの頃の作品である。
遙邨が日本芸術院賞を受賞したのは、1960年(昭和35)64歳のときである。遙邨芸術のトレードマークとも言える狐や狸の描写は、このころから頻繁に画面に表れるようになった。
創作意欲は晩年になっても衰えることを知らず、89歳にして描き始められた、山頭火の俳句を題材とした「山頭火シリーズ」は、遙邨が到達した独自の画境を示す代表的連作となった。
自然を愛し、旅にあこがれた遙邨は、1988年(昭和63)、急性心不全のため93歳にて永眠。